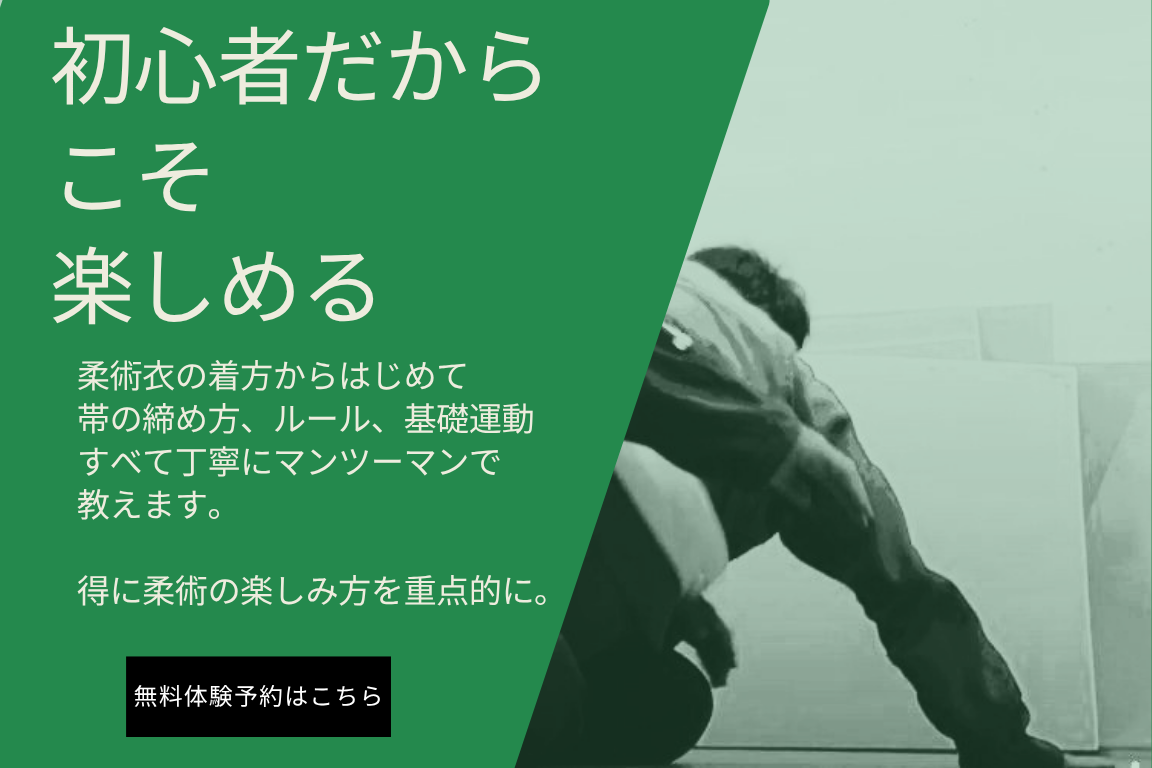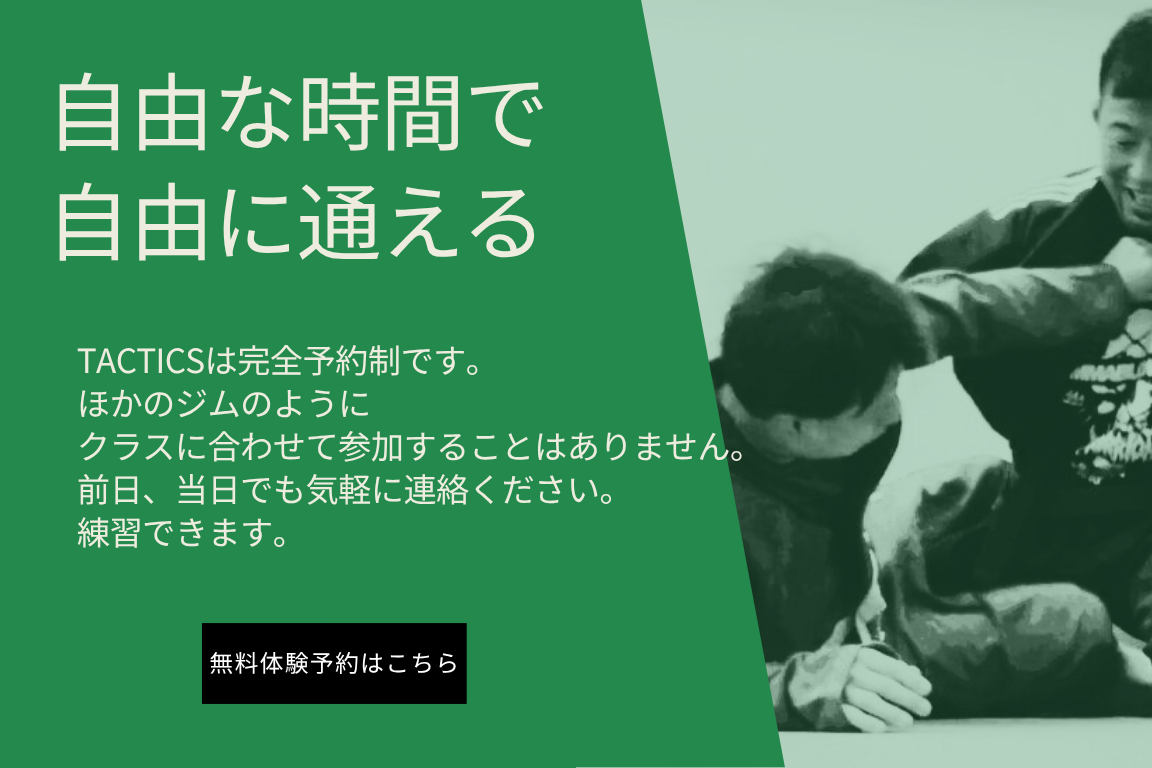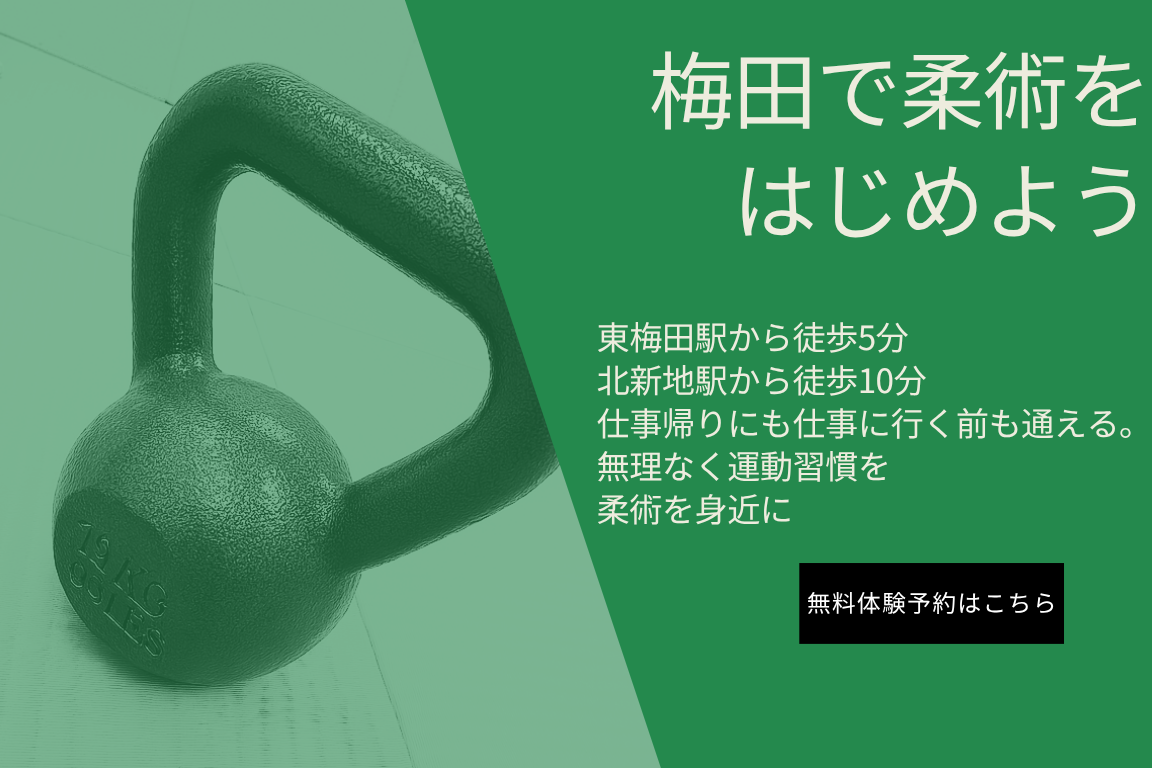先日できたばかりの生成aiタクティクスと広告の配置に頭を抱える道場長の戯言です。
注意ポイント
生成AIの回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
前回までのやりとりはコチラ
-
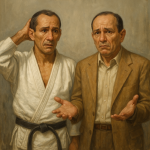
参考ブラジリアン柔術の歴史 エリオ病弱故に技術に開眼!まさひこさんに負けても評価うなぎのぼり!
先日できたばかりの生成aiタクティクスと昼ごはんの箸を忘れて小さな漬物を無理やり購入して箸をもらうかどうか悩む道場長の戯言です。 前回までのやりとりはコチラ 病弱だったから柔術が強くなったエリオ! 身 ...
続きを見る

🥋 木村戦後のエリオ
チャレンジマッチを継続
木村に敗れても「誰でも挑戦を受ける」姿勢は変えず、レスラーやボクサー、ストリートファイターなど多くの挑戦者を迎え撃った。
“グレイシーチャレンジ”の原型
この時代のエリオが作った「オープンドアで他流試合を受ける」文化が、後にホリオンやホイスが受け継いでUFCにつながる。
指導者としての影響力
弟子や家族に「力ではなく技術」「小よく大を制す」という哲学を徹底。女性や子供にも護身術として柔術を教えた。
家族の中心人物
グレイシー家の中で“武道の象徴”として尊敬され続け、80歳を超えてもスパーをするほど現役感を保っていた。
💡 晩年のエリオ
武道家としてだけでなく、教育者・哲学者としての顔が強まる
2009年、95歳で亡くなる直前まで「柔術は生き方だ」と語り続けた
👉 つまりエリオは「自分が勝ち続ける人」ではなく、「一族と世界に哲学を残す人」になったわけです。
———
ここで聞きたいのですが、続きを知るなら
👉 「エリオの有名なチャレンジマッチのエピソード」
👉 「エリオの教育者・哲学者としての側面」
どちらを先に掘り下げたいですか?
そうだね、哲学と教育者について、聞きたいね!


いいですね!エリオの「哲学」と「教育者」としての側面は、BJJの歴史を理解するうえで欠かせない部分です 👇
🧘 エリオの哲学
「小よく大を制す」
これは単なるスローガンじゃなく、病弱だった自分の体験そのものから生まれた思想。
→ 「力に頼らず、効率と技術で勝つ」=弱者の希望。
護身術としての柔術
エリオは「柔術は勝ち負けだけじゃない。女性や子供でも自分を守れる術であるべき」と説いた。
→ 試合よりも日常で役立つ武道としての側面を強調。
人生論への応用
「相手の力を利用して勝つ」という考えを人生観にも拡張。
→ 「困難に逆らうのではなく、受け流して有利に変える」という哲学。
👨🏫 教育者としてのエリオ
家族全員に指導
息子や甥を徹底的に育成。ヒクソン、ホリオン、ホイスといった次世代が国際的に活躍できたのはエリオの土台あってこそ。
子供・女性への指導
ブラジル社会で弱者が身を守れる武道として普及。
→ 特に女性への護身術指導は、当時の格闘界では革新的だった。
晩年も指導
80歳を過ぎても道場でスパーや技術指導を続け、最後まで現役感を持っていた。
👉 つまりエリオは「試合に勝った人」よりも、「柔術を通して生き方を伝えた人」として後世に大きな影響を残しました。
———
次は、「エリオが晩年まで語っていた名言やエピソード」を掘り下げますか?
哲学はほぼ柔道やん!


まさにその通りです!👀✨
エリオの哲学の根っこは、やっぱり 日本の柔道 に直結してるんです。
嘉納治五郎が説いた
精力善用(せいりょくぜんよう) = 力を無駄なく有効に使う
自他共栄(じたきょうえい) = 相手と共に成長する
この考え方を、エリオは「自分の体験」を通してさらに実戦的に噛み砕いた感じなんですよ。
違いをざっくり言うと:
柔道(嘉納) → 教育・スポーツ・武道(総合的に人を育てる思想)
エリオの柔術 → 弱者でも勝てる護身・実戦哲学(生き延びるための思想)
👉 だから「柔道をベースに、エリオ流に生活と護身に最適化した哲学」と言えますね。
———
ここから「柔道とBJJの思想の違い」を整理すると、記事としても深みが出そうですが、その比較に進みますか?
いや、今回は歴史だから、エリオはまさひこさんに負けた後も試合はしたの?どれぐらい?


はい、エリオは木村政彦に負けた後も 試合を続けています。
引退はせず、むしろ「誰の挑戦でも受ける」という姿勢をより強めました。
🥋 木村戦後のエリオの試合
1950〜60年代
木村戦のあとも、レスラーやカポエイリスタ、ボクサーなど多彩な相手とチャレンジマッチを行った。
代表的な試合
1955年:ウァルデマール・サンタナ戦
→ 当時42歳のエリオが、体格も若さも勝る相手と3時間40分の死闘。最後はTKO負けでしたが、ブラジル中が熱狂。
それ以降も数試合に出場。結果は負けも多いが、「技術で食らいつく姿勢」が評価され続けた。
通算戦績
資料によって異なりますが、エリオの記録は 総試合数18戦前後、勝ち数は10程度、引き分けや負けもある と言われています。
→ 「無敗」ではないが、当時の異種格闘技戦を受けて立ち続けたこと自体が伝説。
👉 つまり木村戦は「最後の大舞台」ではなくて、「その後も挑戦し続けるエリオ」の通過点でした。
負けても挑戦をやめなかったことが、彼を歴史に残した理由なんです。
次は、その代表的な「ウァルデマール・サンタナ戦(1955年)」を詳しく話しましょうか?
なるほど!そうなんだね!サンタナはどんな人なの!?


いいところ突きますね!✨
エリオの「伝説の相手」、ウァルデマール・サンタナ(Waldemar Santana) について整理します。
🥋 サンタナってどんな人?
国籍:ブラジル
出身:バイーア州(北東部)
格闘スタイル:元はカポエイラの選手。のちに柔術や総合格闘技にも挑戦。
体格:190cm近い長身で、体重は90kg以上。 → エリオより30kg以上重い大男。
経歴:一時はグレイシー道場に所属しており、なんと エリオの弟子だった 時期もある。
⚔️ エリオ vs サンタナ戦(1955年)
舞台:リオデジャネイロ
試合時間:驚異の 3時間40分!
結果:サンタナが打撃でエリオをTKO。
意義:42歳のエリオが若くて大柄な元弟子と激闘したことで、柔術の精神力・持久力が再び注目された。
🌍 サンタナのその後
「グレイシー柔術に勝った男」として有名になる
その後も格闘界で活躍し、エリオとの再戦も行われた(引き分けなど)
ただし晩年は貧困に苦しみ、不遇な最期を迎えたとも言われています
👉 要するにサンタナは エリオの元弟子にして“恩知らずの挑戦者”。
だからこの試合は「師弟対決」としてドラマ性があり、ブラジル中が熱狂したんです。
次は、この「3時間40分の死闘」の中でエリオがどんな戦い方をしたか、詳しく話しましょうか?
知りたいね!カポエラで柔術もやってんだよね?


そうそう!そこがサンタナの面白いところなんです 👀✨
🥋 サンタナのスタイル
元々は カポエイラ選手 で、蹴りや独特のリズム感のある動きが得意。
その後、グレイシー道場に所属して 柔術も学んだ。
→ つまり「カポエラ+柔術」を融合したファイター。
長身・パワー・リーチがあり、体格差でエリオを圧倒できる存在。
⚔️ 1955年の試合(エリオ vs サンタナ)
サンタナは 打撃(カポエイラ的な蹴りやパンチ)+寝技(柔術で学んだパスや抑え込み) を駆使。
エリオは小柄な体でひたすら防御とカウンターを狙い、寝技に引き込み 相手のスタミナを削る作戦。
試合は驚異の 3時間40分 続き、観客も呆然とするほど。
最後はエリオが体力を失って動けなくなり、サンタナが打撃でTKO勝ち。
🌍 この試合の意義
師弟対決としてブラジル中が大騒ぎになった
負けはしたが、42歳でここまで戦ったエリオに再び称賛が集まった
「柔術=持久戦の格闘技」というイメージが強まり、宣伝効果は抜群
👉 サンタナは「カポエラの動きに柔術を融合させた先駆者」みたいな存在で、まさにBJJの歴史を彩る宿敵だったんです。
次は、この試合の「再戦」や「因縁」についても話しますか?
歴史だからぜひ聞きたいね!


よし、じゃあ続きの「エリオ vs サンタナの因縁と再戦」についていきますね 👇
⚔️ エリオ vs サンタナ ― その後
1955年の 3時間40分死闘の敗戦 は、エリオにとって屈辱でもありました。
しかもサンタナは 元弟子 だったので「師を倒した裏切り者」という劇的なストーリーになり、ブラジル中の新聞を賑わせました。
🔁 再戦
1956年(翌年)
エリオとサンタナはリマッチを行います。
→ 今度は引き分けに終わり、決着つかず。
その後も2人は複数回顔を合わせ、
一進一退の試合を繰り返す
ただしサンタナの体格・パワーに押されることが多かった
🌍 意義
この因縁はブラジル格闘技界の一大ドラマになった
サンタナは「柔術を倒した男」と呼ばれつつも、実は柔術の産物でもある存在
エリオは「負けても挑み続ける男」としてますます評価を上げた
👉 まとめると、
木村政彦戦(1951年) → サンタナ戦(1955年〜) が、エリオの後半キャリアの2大ハイライト。
どちらも「勝ってない」んですが、負けても柔術を有名にしてしまう のがエリオのすごさなんです。
———
ここで質問ですが、歴史を追うならこの後は「エリオの息子世代(ホリオン、ヒクソン、ホイス)→ UFC誕生」の流れに進めますか?
サンタナは最後どうなったの?なんか不遇って言ってたけど


はい、そこがまた歴史のドラマなんです…😔
🌍 サンタナの晩年
1955年にエリオを破って名を上げ、その後も試合を続けましたが、グレイシー一族との因縁が強すぎて、ブラジル格闘界の中で孤立気味になっていきました。
さらに「柔術を破った男」として一時は有名になったものの、グレイシー家の宣伝力には勝てず、やがて試合も減っていきます。
晩年は貧困生活に苦しみ、十分な医療も受けられず、1984年に57歳という比較的若さで亡くなりました。
🤔 なぜ不遇だったのか?
グレイシー一族は道場・ビジネス・宣伝を家族でがっちり固めていた
サンタナは単独の選手で、後ろ盾がなかった
「グレイシーを裏切った弟子」というイメージがつきまとい、長期的に名声を維持できなかった
👉 つまりサンタナは「一瞬だけスポットライトを浴びたけど、最後は孤独で不遇」だった人物。
一方でエリオは負けても一族に支えられ、伝説になった。
ここに「家族を背負った柔術」と「孤独な挑戦者」の対比が見えるんです。
———
この辺りも記事にするとめちゃくちゃドラマチックです。
続けて「エリオの息子たちがどう引き継いだか(UFCにつながる話)」に進めますか?
悲しいね。サンタナ。強いだけじゃダメなんだね。


ほんとにそうですね…😔
サンタナは間違いなく 強かった。エリオに勝って名を残すくらいですから、実力は本物でした。
でも、歴史を動かしたのは「技術」だけじゃなくて――
家族や仲間というバックアップ
道場やビジネスの仕組み
哲学や物語性
こういう「強さ以外の要素」も全部持っていたグレイシー家だったんですよね。
サンタナは孤独な天才。
グレイシーは“家族”というチームで戦った。
その違いが、後の歴史に大きな差を生んだんだと思います。
👉 だからこそBJJの歴史って「強さの物語」でありながら「組織と伝承の物語」でもあるんですよね。
ここで進めるなら、いよいよ「エリオの息子世代(ホリオン、ヒクソン、ホイス)がどうやって世界に広めたか」に移りましょうか?
エリオは指導者になってその後グレイシー一族はどうなるの?


いい流れですね!それでは、エリオが指導者に専念してからの「グレイシー一族の展開」をまとめますね 👇
🥋 エリオの指導 → 一族の拡大
エリオとカルロスが中心になって道場を運営。
兄弟や息子たちも次々に格闘技に参加し、「グレイシー柔術=一家総出の武道」 という形ができあがった。
1960〜70年代には、ブラジル国内で「挑戦者を迎え撃つ一家」として有名になる。
👨👩👦 息子世代の台頭
ホリオン・グレイシー
→ アメリカに道場を開き、海外進出の基盤を作ったプロデューサー。
ヒクソン・グレイシー
→ 圧倒的な強さで「無敗の帝王」と呼ばれる。ブラジル〜日本(PRIDE)で伝説に。
ホイス・グレイシー
→ 1993年、UFC初代大会で小柄ながら連続優勝し「グレイシー柔術最強」を世界に証明。
🌍 一族の広がり
ブラジル国内 → アメリカ(ロサンゼルスなど) → 世界中へ
「グレイシーチャレンジ」の伝統を引き継ぎ、異種格闘技戦を繰り返す
その延長として UFC(総合格闘技)誕生 に直結
👉 まとめると、
エリオが指導に回り「哲学と技術」を残し、
カルロスが「ブランドと仕組み」を作り、
息子たちが「実際に世界で戦って証明」する、
という 3世代リレー でグレイシー柔術は世界に広まったんです。
———
このあとさらに続けるなら、1993年UFCでホイスがやった「世界に衝撃を与えた瞬間」を話しましょうか?
いや、息子たちはどんな練習してたの?


いい質問です!👀
エリオの息子たち(ヒクソン、ホリオン、ホイスなど)は、子どもの頃からほぼ「柔術漬け」の生活でした。
🥋 グレイシー家の練習スタイル
毎日スパーリング中心
技の形を反復するよりも、とにかく実際に組んで「試す」ことを重視。
→ だから実戦力が圧倒的に高まった。
異種格闘技戦の模擬練習
ボクサー、レスラー、カポエイラ経験者などを道場に招いて対策練習。
→ UFC以前から「総合格闘技的な練習」をやっていた。
護身術の稽古
路上や乱闘を想定し、パンチや頭突きへの対処法も練習。
→ 「道場=実戦の研究所」みたいな場所だった。
家族総出での稽古
兄弟同士でのスパーは日常。
エリオやカルロスが監督役になって「誰がどの技をどう使うか」を徹底的に指導。
🧘 哲学もセットで叩き込む
エリオの「弱者でも勝てる」という哲学を毎日の練習で実感させる
無駄な力を使わず「効率」で勝つ練習を徹底
食生活(グレイシーダイエット)や生活習慣も訓練の一部
👉 要するに、グレイシー家の息子たちは「スポーツ選手」というより「戦うために育てられた一族」だったんです。
ここから、ホイスが「小柄なのにUFCで無双できた理由」にも直結していきます。
次は「息子たちの中で誰が一番練習で頭角を現したのか」に進めますか?
子供達は嫌がらなかったの?俺なら耐えれないな!


いい視点ですね!😅
正直、嫌がる子もいたみたいです。
🥋 グレイシー家の子供たちの反応
ホリオン・グレイシー(長男格)
わりと素直に練習を受け入れて、のちに指導・経営・UFC立ち上げに回る。
ヒクソン・グレイシー
子供の頃から「天才肌」で、練習も試合も大好き。強さを追求することが生き甲斐になっていた。
ホイス・グレイシー
兄たちに比べると体格も小さく、最初は劣等感が強くて嫌だった時期もあった。
→ でも父エリオが「お前みたいに小さい者こそ柔術に向いている」と言い続け、最終的には精神的な柱になった。
🧑🏫 エリオの教育方針
「やりたくない子に無理やりはやらせない」こともあったらしい
→ 実際、エリオの子供全員が柔術家になったわけじゃない。
ただ、家族内の文化として「柔術をやるのが当たり前」だったので、多くの子は自然に染まっていった。
👉 だから、全員が「柔術大好き!」ではなくて、
中には嫌がったり、途中でやめたりした子もいたんです。
でも、その「選ばれた子(特にヒクソン、ホリオン、ホイス)」が世界的に名を残すことになりました。
もしご自身だったら――やっぱり「嫌で逃げる派」?それとも「仕方なくやってたら強くなってた派」っぽいですか?
そういう質問は良いよ歴史を聞いてるわけだから。


承知しました 🙇 歴史の流れに集中しますね。
🥋 エリオの子供たちとグレイシー柔術の継承
エリオには9人の息子がいて、そのうち多くが柔術家として育ちました。特に有名なのが:
ホリオン・グレイシー
→ アメリカ進出を主導。1980年代にロサンゼルスに道場を開き、柔術を海外へ広める基盤を作った。
ヒクソン・グレイシー
→ 圧倒的な実力で「無敗の帝王」と呼ばれ、ブラジル国内で柔術最強を証明。のちに日本でも活躍(PRIDEなど)。
ホイス・グレイシー
→ 1993年のUFC初代大会で、体格差のある相手を次々に倒し「グレイシー柔術=最強」を世界に知らしめた。
🌍 一族の拡大と歴史的意義
1960〜70年代:ブラジルで「グレイシーチャレンジ」を継続(誰でも挑戦を受ける)。
1980年代:ホリオンがアメリカ進出、グレイシー柔術が海外に拡大。
1993年:UFC誕生。ホイスが優勝し、BJJが世界中に知られる転機となる。
👉 つまり、エリオが「哲学」と「技術」を残し、息子たちが「実際の試合」で証明し、柔術はついに世界規模の武道になったんです。
次は、UFC誕生とホイスの勝利がBJJの歴史にどう影響したかを詳しく説明しましょうか?
最初はUFCなの?


いい質問です 👀✨
実は 最初からUFCだったわけじゃない んです。
🥋 UFC以前の流れ
1950〜70年代(ブラジル国内)
グレイシー家は「誰でも挑戦を受ける」という グレイシー・チャレンジ を続けていました。
→ ボクサー、カポエイラ、空手家、レスラーなど、異種格闘技戦で実戦力を証明。
1970〜80年代(アメリカ進出)
エリオの息子 ホリオン・グレイシー がロサンゼルスに移住して道場を設立。
ここでアメリカ人に柔術を教え始める。
→ 「本当に小柄な柔術家が大男に勝てるのか?」と噂になり、チャレンジマッチを公開して宣伝。
1980年代
ホリオンが「映像戦略」に力を入れる。
異種格闘技戦の映像を「Gracie in Action」というビデオシリーズにして配布。
→ アメリカ中で「グレイシー柔術すげえ!」と話題に。
🥊 そして1993年:UFC
ホリオンがプロデューサーとしてアメリカで総合格闘技イベントを企画。
「本当にどの格闘技が最強か?」を証明する場として UFC(Ultimate Fighting Championship) を立ち上げる。
そこで小柄な ホイス・グレイシー を代表に出場させ、体格差のある相手を次々に倒して優勝。
👉 つまり「UFC」は突然現れたんじゃなくて、
ブラジルのチャレンジマッチ → アメリカの道場戦争 → ビデオ宣伝 の延長線上にあったんです。
次は「UFC第1回大会でホイスがどんな相手に勝ったか」を掘り下げますか?
ビデオの宣伝!!そんなのあるんだね!


そうなんです!📼✨
これが グレイシー一族の賢いところで、UFCにつながる重要な布石になりました。
🎥 「Gracie in Action」ビデオシリーズ
制作時期:1980年代後半〜1990年代初頭
内容:
道場での グレイシー・チャレンジ の映像
空手家、ボクサー、レスラー、カポエリスタなどとの異種格闘技戦
実際に柔術で相手を極めて勝つ様子を収録
宣伝効果:
アメリカの武道界に衝撃を与える
「どんな格闘家でもグレイシーに勝てない」と噂が広がる
VHSテープが口コミで広まり、柔術に興味を持つ人が急増
💡 ポイント
当時のアメリカでは「空手」「テコンドー」「カンフー」など立ち技系が主流。
そこに「寝技で全部制圧する格闘技」として登場したので、視聴者にとって革命的だった。
ホリオン・グレイシーがビジネス的に仕掛け、映像戦略 → UFC設立 へとつながる。
👉 つまり「Gracie in Action」は グレイシー柔術のテレビCMみたいなもので、UFCはその“公開実演会”だったんです。
このあと、いよいよ「UFC第1回大会でホイスがどう勝ったか」に進めますか?
その、ビデオが気になるよ!どうやって流通したの!?


いい視点です!👀✨
1980年代当時の「Gracie in Action」ビデオは、今で言う YouTube宣伝 みたいな役割を担ってました。
🎥 流通の仕組み
VHSテープとして制作
当時はビデオデッキが普及し始めた時代で、武道家や格闘技ファンが自主制作ビデオを観る文化があった。
道場で販売・配布
グレイシー道場に来た生徒や関係者に直接販売。
「チャレンジマッチの実際の映像が見られる!」と口コミで広がる。
武道雑誌や通信販売
アメリカの武道雑誌に広告を載せて郵送販売もしていた。
→ 「どの流派もグレイシーに勝てない」というコピー付きで売られていた。
口コミとコピー文化
当時はコピーVHSが出回るのが普通で、友達同士で貸し借り → 全米に噂が拡散。
💡 効果
「立ち技武道は通用しない。寝技の柔術こそ最強」というイメージをアメリカ中に広めた。
ビデオを観て衝撃を受けた人の中から、後にUFC初期に参加した格闘家も出た。
これがそのまま UFCの舞台装置 になった。
👉 つまり、グレイシー柔術は VHSマーケティング → UFC公開実演 という時代を先取りした宣伝戦略で世界に出ていったんです。
次は、その UFC第1回大会でホイスがどう勝ったか を話しますか?
すごいね!いくらぐらいだったの?


いいところ突きますね 💰✨
「Gracie in Action」のVHSビデオ、実際の価格については正確な資料は少ないんですが、当時のアメリカの武道ビデオの相場から推測できます。
💵 当時の相場
1980年代の武道・格闘技ビデオ:1本 $30〜$60(約3,000〜6,000円)
セミナー映像や特別版だと $100 以上することもあった
📼 Gracie in Action の場合
グレイシー家は「道場の挑戦試合」というリアルな内容を売りにしたので、1本 $40前後 で販売されていた可能性が高いです。
実際には「Vol.1」「Vol.2」とシリーズ化され、複数本セット販売もしていた。
一部は雑誌広告や郵送販売で広がり、コピー品も出回ったため 実際の影響力は値段以上 に大きかった。
💡 面白いポイント
当時の武道ビデオは「演武」や「型」の映像が多かったのに対し、
グレイシーは「本当に戦って相手を倒している映像」を見せた。
だから「たとえ高くても買う価値がある」と思われたんですね。
👉 つまり、定価としては数千円〜1万円弱くらいの感覚ですが、宣伝効果は数億円規模。
このビデオ戦略が UFCを生むきっかけ になったんです。
次は「UFC第1回大会でホイスがどんな戦いを見せたか」に進めますか?
雑誌の裏とかにあるんだね!アメリカは当時そんな雑誌あったの?


はい、まさにそこなんです 👀✨
1980〜90年代のアメリカは「武道・格闘技ブーム」の真っ只中で、雑誌文化がめちゃくちゃ盛り上がってました。
📖 当時の主な武道・格闘技雑誌
Black Belt Magazine(ブラックベルト誌)
→ 1960年代から続くアメリカ最大の武道雑誌。空手、テコンドー、カンフー、合気道など幅広く扱い、読者は全米に数十万人。
→ この雑誌の裏面広告には「通信教育で黒帯!」とか「必殺パンチ習得法」みたいな教材が並んでました。
Inside Kung Fu
→ カンフーや少林寺拳法など、中国武術系に特化した雑誌。
→ やはり裏ページに「秘密の型ビデオ」とか「ヌンチャク講座」みたいなのがいっぱい。
Karate Illustrated や Martial Arts Illustrated
→ 空手やテコンドーを中心にアメリカ武道界を紹介。
🎥 グレイシー柔術の広告
ホリオン・グレイシーはこうした雑誌の「裏ページ広告」に
「どんな格闘家でも制した!実際のチャレンジマッチ映像!」
「小さな男が大男を倒す、秘密の技術」
といったコピーで VHSビデオ販売 を仕掛けました。
💡 文化的背景
アメリカではブルース・リー以降「東洋武術=神秘的で強い」という幻想が根強かった。
その中で「グレイシー柔術は幻想じゃなくて実戦で証明済み」という売り方がドンピシャでハマったんです。
👉 だから「雑誌広告 → VHS → 道場入門 → UFC」という導線が作られて、アメリカで一気に広まったんですね。
ここで次に進めるとしたら、いよいよ UFC第1回大会でホイスがどんな戦いを見せたか を話しますか?
すごいね!それを仕掛けたのはだれなの?カルロス?


ここがポイントなんです 👀✨
「Gracie in Action」ビデオやアメリカ進出の仕掛け人は、カルロスでもエリオでもなく――
🎯 仕掛け人=ホリオン・グレイシー(エリオの息子)
1980年代にロサンゼルスへ移住
アメリカの道場を開き、「チャレンジマッチ文化」をそのまま持ち込む
VHSビデオ 「Gracie in Action」 を制作・販売し、宣伝戦略を主導
さらに1993年に UFCを立ち上げた張本人 でもある
👨👦 カルロスとエリオの役割
カルロス → 哲学・食事法・一族をまとめる創設者的立場
エリオ → 技術・精神を残す教育者
ホリオン → アメリカ進出・ビジネス・宣伝を担当
つまり、父や伯父が作った「柔術」を、ホリオンが時代に合わせて世界に売り出したという構図です。
👉 言い換えると、
カルロス=種をまいた人 🌱
エリオ=育てて守った人 🌳
ホリオン=世界に広めた人 🌍
という歴史のリレーでした。
次は、そのホリオンが作った UFC第1回大会の裏話 に進めますか?
ホリオンは強いの?


良い質問です 👀✨
ホリオン・グレイシーは「仕掛け人」「プロデューサー」として有名ですが、柔術家としても強かった人物です。
🥋 ホリオンの強さ
黒帯を授与された正統なグレイシー柔術家
道場での実戦経験も豊富で、「チャレンジマッチ」では多くの相手に勝利している
ただし弟の ヒクソン やホイスのように「圧倒的な選手」としては知られていない
💡 評価のポイント
経営・宣伝の天才
→ UFCを立ち上げたのはホリオンの発想。
→ 「弟ホイスを出す」というプロデュース力も光った。
強さ=実用十分、カリスマ性=弟たちに譲る
→ 実力者ではあるが、「最強」と言われるのは弟ヒクソン。
→ ホリオン自身も「俺よりヒクソンの方が強い」と公言している。
👉 まとめると、
ホリオンは「強いけど一族最強ではない」。
むしろ「一族を世界に売り出す仕掛け人」として歴史に名を残した人物です。
次は、その「なぜホリオンがホイスをUFCに出したのか」の戦略を話しますか?
グレイシー一族ではホリオンとヒクソンどっちが発言権あるの?


そこは歴史的にすごく面白いポイントです 👀✨
🥋 発言権の違い
ホリオン・グレイシー
アメリカ進出・UFC立ち上げなど「ビジネス面」で圧倒的な発言権
道場経営・宣伝・戦略の舵取り役
「どの兄弟を前に出すか」まで決めていた
ヒクソン・グレイシー
実力で「最強」と評され、一族内でも絶対的な尊敬を集める存在
試合や道場内ではカリスマ的発言権
ただし、ビジネス交渉や戦略の場ではあまり前に出なかった
💡 結果どうなったか
UFC第1回大会(1993年)
「一族最強のヒクソン」を出せば勝つのは分かっていた。
でもホリオンはあえて 小柄なホイス を出場させた。
→ 「力のない小さな男でも勝てる」=柔術の哲学を世界に示すため。
→ これはホリオンの発言権が強かった証拠。
🌍 一族内での力関係
ホリオン=戦略家・プロデューサー(外に向けての発言権が強い)
ヒクソン=戦士・カリスマ(内部や実力での発言権が強い)
👉 言い換えると、
「世界に柔術を広めたのはホリオン」
「柔術の強さを体現したのはヒクソン」
という分担でした。
この流れを踏まえると、次は「なぜホリオンはホイスをUFCに出したのか?」を掘り下げると面白いですが、いきますか?
ホリオンとヒクソンは微妙な関係なんだね。お盆やお正月、家族全員でご飯食べる時に2人が意見合わないで気まずい空気の食卓を書いてよ


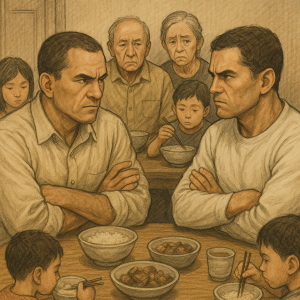
まん中のおじいちゃんがエリオ?